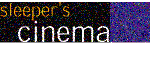
|
|
|
|
|
|
|
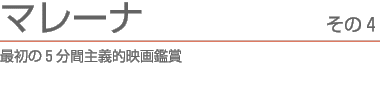
���ƃt�@�V�X�g�}�A����ɐS������J�X�e���N�g�́i��j�l�����A���ꂩ���l�����̉e�����ԐړI�Ɏ�q�ǂ�����������ɁA���̔��̋ɂɋa�i���}���[�i�j��u�����\�}�����V�[�N�G���X�́A���̗������痣�ꂽ�Ƃ���Ƀ��i�[�g��z�u����B������^�]�ŋC�����グ�Ă���i�K�̃��i�[�g�́A���̉e���������ĎQ�����ԊX�̐l��������߂���łȂ��߂Ă��邵�A�a���Ă��E���ėV�Ԏq�ǂ������̒��Ԃɂ������Ă��Ȃ��B����ɁA�܂��}���[�i�̑��݂�m��Ȃ��B
������A���̃V�[�N�G���X�ňʒu�t�����郌�i�[�g�̊�́A�X�̐l�����������Ӗ����狗����u�����u�J�����v�̃��^�t�@�[�ɂȂ�B
�����Ƃ��A�������܃}���[�i�Ƀw���w���ɂȂ�̂�����A�q�ϓI�Ɂu������u�����v��ł͂���Ȃ��킯�����ǁA���Ȃ��Ƃ����j����̌������痣��āA���������̂������ƂȂ��߂Ă������Ƃ����f��̎����Ƃ��ċ@�\���邱�ƂɂȂ�B�f����ςĂ���Ԃ́u�悭�l���Ă݂�A���i�[�g���ėv����ɃX�g�[�J�[�Ȃ�ȁv�Ƃ�����ÂȔ��f���I�グ����邱�ƂɂȂ�̂́A���̃V�[�N�G���X�����i�[�g�̊���u�J�����v�ʒu�ɐ����邩�炾�Ǝv���B
�Ƃ͂����A���łɃ��i�[�g�́i�����ʂ�j�����ɂ��t�@�V�X�g�������̌������E�ъ���Ă��Ă���B�ړ�����ނ́u��v���x���鎩�]�Ԃ̃t���[���́i�C�^���A���N���������₪�ĘA���R����������k�サ�Ă���j�A�t���J���A�M�A�́i���z�������j�t�����X���A�����ă`�F�[���̓V�`���A���Ƃ����u�J�X�^�����C�h�v�B��l�ɋ߂Â����߂̂����ȒʉߋV��̏ے��Ƃ��Ďg���邳�܂��܂ȃ��m�i���Y�{���A�����A���b�\���[�j�̓��A���فAetc.�j�̐悪���Ƃ��Č���鎩�]�Ԃ��炵�āA���łɃC�^���A�́A�Ƃ����̂��V�`���A�̐����I�������n�b�L���N�b�L���f���o���Ă��邱�ƂɂȂ�B
�Ƃ����킯�ŁA���̖`���̃V�[�N�G���X�̃G�s�\�[�h�ł́F
�E��������Q�O�̃G�l���M�[
�E���̃G�l���M�[���W�߂��A�X�P�[�v�S�[�g�Ɍ�������\��
�E���������������f���o���i���̂Ƃ���j���C�Ȏ���
��������A���ꂩ��͂��܂�}���[�i�̕�����ے��I�ɗ\�����邱�ƂɂȂ�B
�ŁA���낢������]�Ȑ܂��o����ɁA�J�X�e���N�g�̊X�𑖂蔲����ԁ����삷��Q�O���X�̑S�i���L��Ƃ�����ɁA�f��͂܂�����蓯���V�[�N�G���X���J��Ԃ��B�ł��A�J�b�g�̒��g���K���b�ƕς���Ă���B����Ԃ̓A�t���J�������k�サ�Ă����A���R�̂��̂����A�Q�O�͔��t�@�V�Y���Ɋ��삵�Ă���B�}���[�i�͋��e�����t�@�V�X�g���̏��ɂȂ��Ă��āA�Ί�̃��i�[�g�͘A���R�̎Ԃɏ���Ă���B
�����āA�}���[�i���n�ʂ����ƂɂȂ�B�a�̂悤�ɁB
���̊Ԃɉ����ǂ��ς���āA�㔼�̃V�[�N�G���X���ǁ`�̂��`�̂ƌ����o���ƃL�����Ȃ��̂ł�߂邯�ǁA���Ƃقǂ��悤�ɁA�`���̃V�[�N�G���X����X�܂Ŕ��������̂ł������B
�ƁA�����ƁA���̉f��͍ŏ�����Ō�܂Ŏ����т����\���́A�ƂĂ��ƂĂ������f��Ɍ����邩������Ȃ��B�ł��A�t�@�V�X�g�}�����������������u���A���i�[�g�̐����̃v���Z�X�ŏd�v�Ȗ�����������ʉߋV����ŏ�����Ō�܂ŃR���g���[�����Ă���͔̂ނ̕��Ȃ̂��B�ł��A���̕`�������R�~�J���Ɍ֒����ꂷ���Ă��āA�{���͒ʑt�ቹ�̂悤�ɕ\�̃����f�B�ɋ��������Ă���͂��̕��e�̉e�������_���A�������s���������������̂��B
June 20, 2001
|
|
|
|
|
|
|