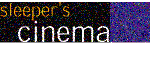
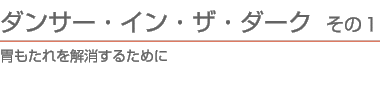
「ダンサー・イン・ザ・ダーク」の魅力の半分以上はビヨークの存在感にある。
というのが正しいにしても、この存在感に似たものをどこかで観たような気がしてしょうがなかった。存在感というのか、主人公セルマの類型みたいなものを確実に知っている、という気がしていたのだ。
そういうわけで、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」を観てからというもの、それが何だったのかが気にかかってしょうがない。
工場で働くシングル・マザーの話でこんなやつはなかったか?とか、絞首刑になる映画で似たのがなかったか(でも、「デッドマン・ウオーキング」じゃないよな)?とか、女性が主人公のミュージカル?などなど、いろいろと考えてみたけど、ぜんぜん結論が出ない。
こういう場合は、いきなりそれに似た何かを探そうとするからいけないのだ。ビヨークの圧倒的な存在感、とか何とか言いながら、それが具体的に何かをハッキリさせないから、「それに似た何か」を思い出すための本当のキーワードが浮かんでこないのである。
じゃ、ビヨークの存在感って何よ?
そもそもこの映画、とてもヨーロッパ的である。ハリウッドだったらヤブカラボーにハッピーエンドな映画にして安心できちゃうところを、しっかりと厳しい現実認識を中心に据えている。でも、その中に希望を見いだそうとする理想主義的なスタンスを捨てていない。
こうしたバランス感覚は、例えばヴェンダースの「ベルリン天使の唄」なんかと共通していて、現実は現実として厳しいことを前提にした上で、(「transcendental」なもの、って何て言ったらいいんだろう?)地上のモノゴトとは別の秩序なり方向なりを追い求めていく姿勢が貫かれている。去年公開されたドイツ映画の「ラン・ローラ・ラン」にしても、ありうべき現実の形をプレイバックで見せることで、地上の現実と天上(というのか何というのか)の現実を同時に見せる、という手法が取られている。古いところでは「コミットメンツ」、それから「フル・モンティ」とか「ブラス」、現在公開中の「リトル・ダンサー」にしても、(ハリウッド寄りではあるけれど)そうした二通りの現実認識を基盤に据えているように思える。
そうした映画で一番の要になるのが、二つの相反する現実をリンクする媒体に何を選ぶか、という点だと思う。
ヴェンダースはブルーノ・ガンツに天使を演じさせることでこの問題を解決しているし、「ローラ・ラン」だとストーリーを途中から繰り返すことで、事実上この問題を棚上げにしている。「フル・モンティ」はストリップという、現実ではあるけれど非日常に類する行為によって二つの現実が媒介されている。それからよくあるのが、音楽やダンスといったパフォーミング・アーツによって、現実と非現実をつなぐ、というパターン。
というわけで、こうした媒介の役割を果たすものは、「卑俗な」現実と「崇高な」非現実をうまいこと繋げる機能を持っていないといけない。天使は古来からまさしくそのような役割を果たしてきているわけだし、肉体を露出するストリップという行為だって、卑俗/崇高の仲立ちをしている。パフォーミング・アーツについては言うまでもない。
(つづく)
|
|
|
|
|
|
|