
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
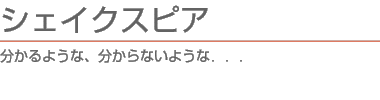
�u�l���͕����e�@�t�D�D�D�v�̂����Ƃ����Ȃ��������ȂƎv���Ė{�I��T������A�V�����ɂ���o�Ă���g�c����́u�V�F�C�N�X�s�A�v���������B
��X�̖��́A�������e�����l�̂܂�Ȃ��|�l�ŁA
����̏�Ŏb������g�ɂȂ�����A�������肵����ɁA
���̂܂܂ǂ����֍s���Ă��܂��̂��B�����
���s�����ĕ�������b�ŁA���X�����ĈА����������A
���̈Ӗ�������͂��Ȃ��̂��B
�Ȃ�قǁB��͂�i���������B�������A�����ƌ����ɉ��s�����킹�Ă���B�i������u�ǂ����֍s���Ă��܂��̂��B����́v�ʼn��s���邱�ƂɂȂ�B�j�������B
���Ȃ݂ɔނ̓}�N�x�X���_���J�����E���ׂ��Q���ɓ����Ă�����ʂ�������āA����Ȃ��Ƃ������Ă���F
�ނ͍����ɂȂ��S���猻�݂̍������E�����Ƃ��v���������̂ł��邪�A���ۂɎE�����ɂȂ��āA�ނ͂������̎E�����ƂɌ������Ď�����ڂ̂ł���B�������Ȃ�������ɂȂ�Ȃ�����ł͂Ȃ��āA�����ɂȂ낤�ƌ��߂��������E�����Ƃ́A�ނɂ��ł��Ȃ�����ł���B
�������͋g�c����B���x�ǂ�ł����ǂǂ��������ƂȂ̂������ς�킩��Ȃ��B�ł��A�}�N�x�X���������킯�̕�����Ȃ����_��Ԃɂ���Ƃ������Ƃ͂�������`����Ă���B
�g�c����̕��͂́A�Ƃ�ł��Ȃ������ɁA���Ȍ��ɗv�_���X�p�b�Ə��������͂̊ԂɁA�ڂ���ƕ��������悤�ɂȂ邯�ǁA����ǂ�ł��ŏI�I�ɂ͂����肵�Ȃ����͂����ꍞ��ł邩��ʔ����B
�ŁA�����ɊȌ��ɗv�_���X�p�b�Ə����Ă���g�c����̕��́F
�m�G���U�x�X���̎���́n����Ƃ͂��̂悤�ɂ��āA������̍�i�ŊϏO���\������G���ȕ��q�̖}�Ă�������H�v�����A���̌���Ŕނ͑S�����R�ɏ������Ƃ��ł����B���_�_���A��ɂ��ׂ��������A�}�Č��I�Ȍ��ʂ̖��Ɋ|���ċ��e�����Ɠ����ɁA�V���ƁA�펯�ƁA�o���ƁA��҂��L��������i�̐���ɌX����ꂽ�B�����Ă��̌��ʂƂ��Ă̔ނ̍�i�́A�ϏO�Ɠ��l�ɑ��ʓI�ȁA�L���ȓ��e�������ƂɂȂ����̂ł���A���ꂪ���铝��������Ă���Ȃ�A���̊ϏO���G���ł͂Ȃ��A�����ӂ̑��ʂȑ��݂������̂ł����āA���l�b�T���X�̉p���l�Ƃ������̂������Ɍ�����̂ł���B
����́u�G���U�x�X����̉����v�Ƃ����͂̂�����Ō�̒i���B�������B
�|���t�H�j�[�Ƃ����T�O���g���āA�o�t�[�`���Ƃ������V�A�̕��|�]�_�Ƃ��A�h�X�g�G�t�X�L�[�̏������s�ލ��ׂƂ������ꊴ���G���G���Ƙ_�����]�_�����邯�ǁA������ėv����ɂ����������Ƃ��ϋq�Ȃ��ɂ�����Ƃ������ƂȂ�ȁB�������킸����i���ŏ����Ă���B
����ɂ��Ă��A�u�����ɂȂ낤�ƌ��߂��������E�����Ƃ́A�ނɂ��ł��Ȃ��v����A�u�E�����ƂɌ������Ď�����ڂv�}�N�x�X�I���ċ�̓I�ɂǂ��������ƂȂ낤�H
�吷����c���ƒlj�����������邩��A�r������C���ɂȂ��Ă������ǁA�������ގv���ōŌ�܂ŐH�ׂ�ׂ�������ڂA�̊g�勭���łƂ��H�܂����ˁB
May 16, 2000
|
|
|
|
|
|
|